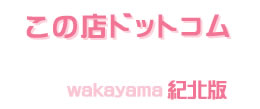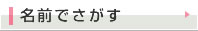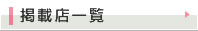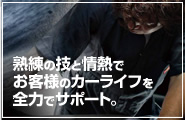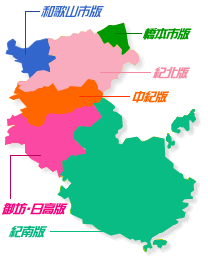おすすめ商品・サービス 〜 全 3 件 〜
掛け軸の表装

掛軸は、書や絵を引き立てる装飾物とされており、書・絵や用途によって表装形式というものがあります。
例えば、仏事に使われる場合は、仏表具で仕立てます。
四国八十八ヶ所・西国三十三ヶ所等は、中央にお大師様や観音様がおられます。
伝統的掛け軸は、表装過程で和紙を縦に繋ぎ合わせなければなりません。その際に、お大師様や観音様のお顔や上半身部分に繋ぎ目が入らないようにします。
例えば、仏事に使われる場合は、仏表具で仕立てます。
四国八十八ヶ所・西国三十三ヶ所等は、中央にお大師様や観音様がおられます。
伝統的掛け軸は、表装過程で和紙を縦に繋ぎ合わせなければなりません。その際に、お大師様や観音様のお顔や上半身部分に繋ぎ目が入らないようにします。
額装も承っております。

表具の代表形式である額装。
現在行われている紙貼りの額は、中国の木彫の額から発展したものといわれています。
本来、額は室内ではなく軒下などに掛けられておりましたが、紙貼りの額の出現によって初めて室内の額装が可能になりました。
現在行われている紙貼りの額は、中国の木彫の額から発展したものといわれています。
本来、額は室内ではなく軒下などに掛けられておりましたが、紙貼りの額の出現によって初めて室内の額装が可能になりました。